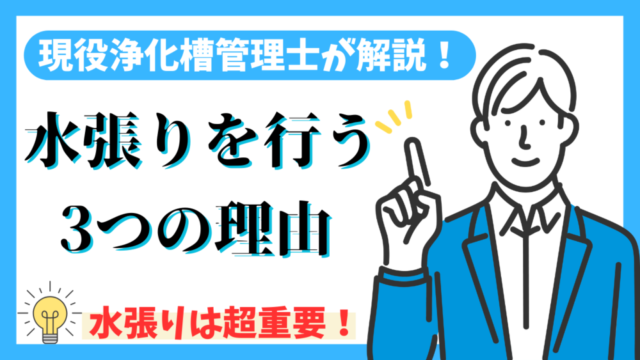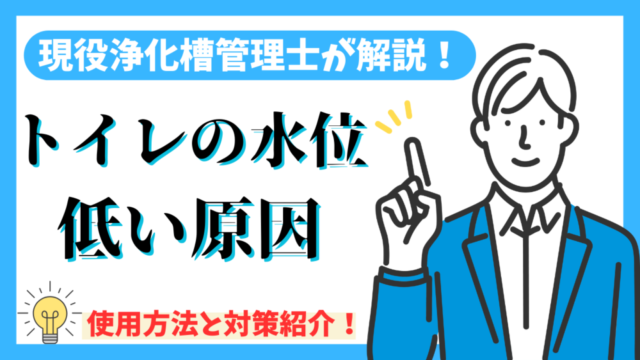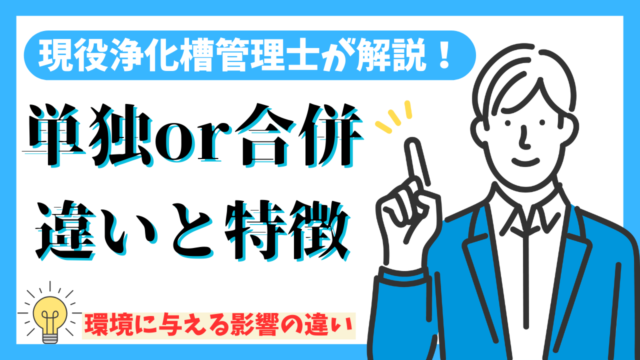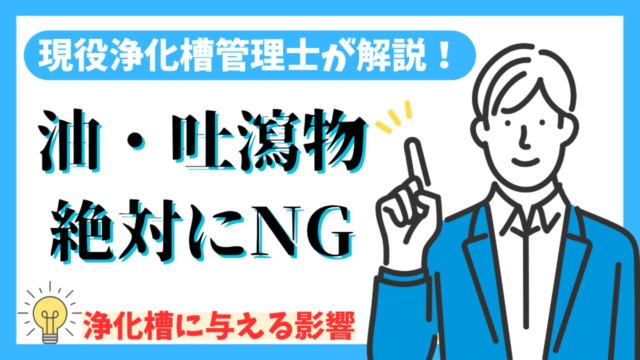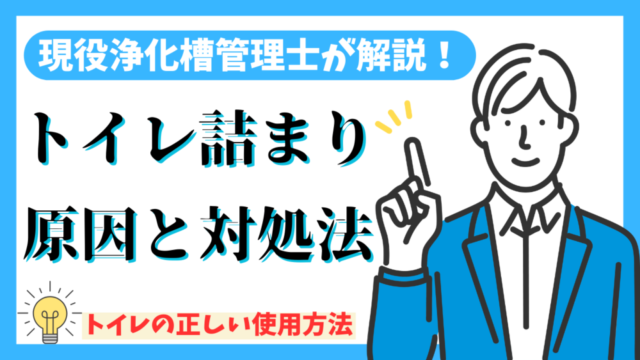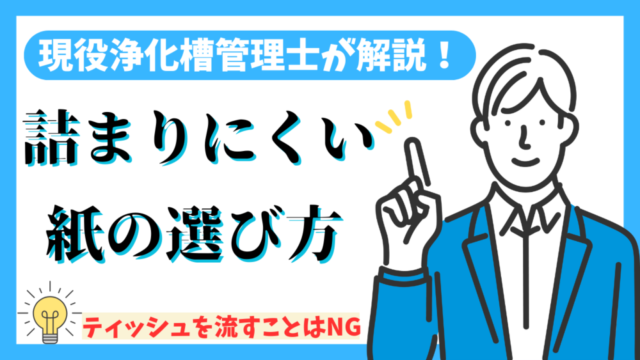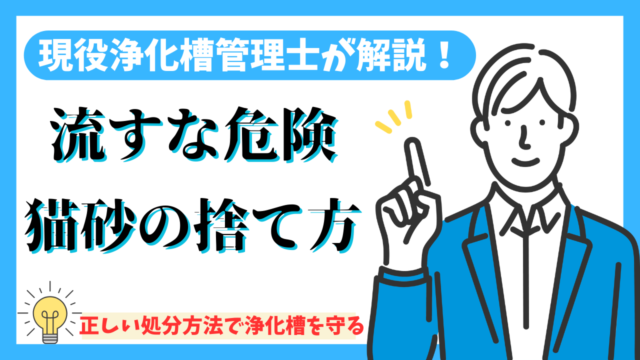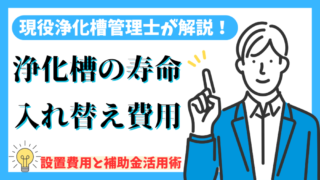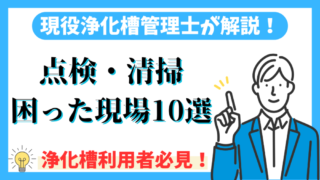【災害対策】浄化槽トイレを安全に使う方法|使用できないケースと揃えておくべき備蓄品紹介!
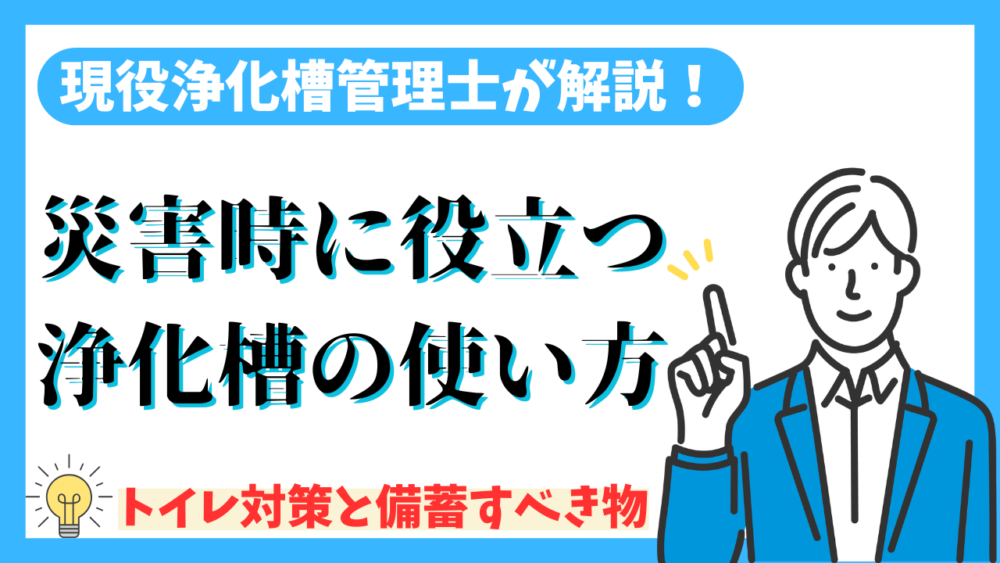
地震や台風などの自然災害が起きた際、最初に困るのがトイレの問題です。特に浄化槽を使っている家庭では「災害時に使用できるのか」「逆流や故障の心配はないか」といった不安の声が多くあります。
この記事では災害時における浄化槽トイレの使い方や注意点、今すぐ備えておきたい備蓄品について解説します。
浄化槽が災害に強いと言われる理由
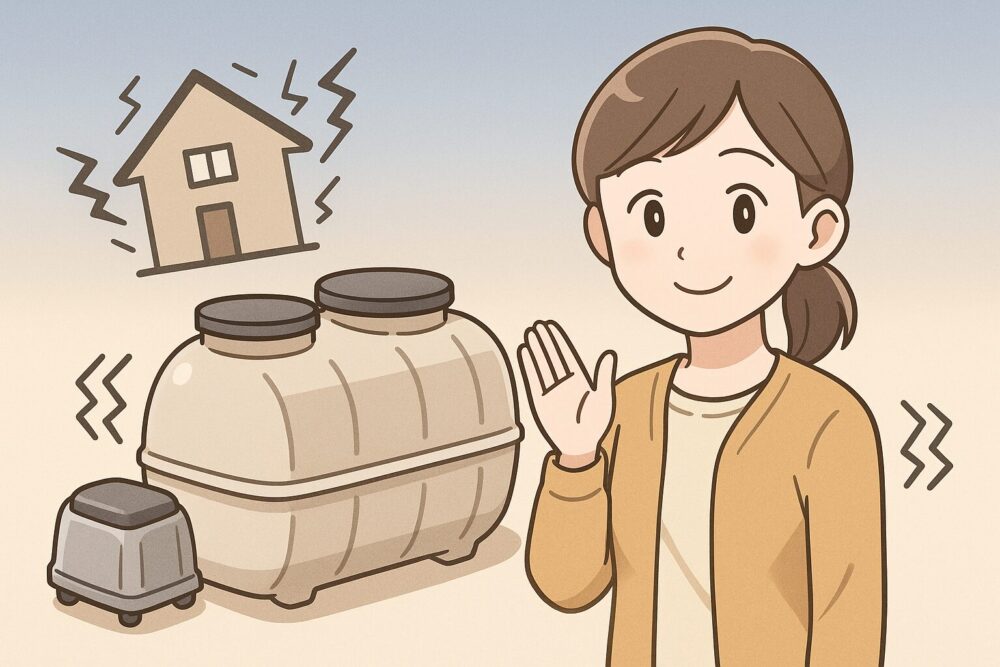
浄化槽は地震などの災害に強い構造です。特に近年の浄化槽は材質が改良されており、本体が破損することはほとんどありません。
液状化などの地質の影響で沈下や浮上が発生することはありますが、本体が破損するケースは多くありません。災害時に多いのは、本体のずれによって配管が外れるトラブルです。
浄化槽は被災しても早期に復旧でき、修理開始から1週間~10日で使用を再開できます。修理可能な状態であれば、すぐに工事を始めることも可能です。一方、下水道は仮復旧までに平均30日、本格復旧になると3~6か月以上かかります。
早期に使用を再開できる点で、浄化槽は下水道よりも実用性に優れています。
災害時でも浄化槽が使えるケース
結論から言うと災害時でも浄化槽は使用できます。ただし、以下の条件が必要です。
- ブロワーが正常に稼働している
- 配管が外れていない
- 浄化槽本体に破損がない
- 消毒剤が設置されている
水の使用は必要最小限にとどめ、大量の排水は避けましょう。浄化槽管理業者への早期連絡が重要です。
災害時に浄化槽が使えないケース

災害時、浄化槽が使えないケースは以下のとおりです。
- 浄化槽が浸水している
- 浄化槽が浮上している
- 浄化槽本体の漏水や配管が外れている
- 放流先に詰まりや異常が発生している
浄化槽が浸水している
浄化槽が浸水すると、雨水や泥が内部に入り込み、処理機能が低下します。浸水している状態では水を流しても排水がうまくできません。
ブロワーが雨や雪で水没すると空気を送れなくなり、浄化槽の処理能力が低下します。空気が不足すると、悪臭の発生や汚水のあふれにつながります。水没したブロワーには漏電の危険もあるため、使用前には必ず管理業者に点検を依頼してください。
放流ポンプを使用している場合、水没によって処理水が排出できず、満水状態になることがあります。トイレの排水ができなかったり、汚水が逆流したりするため注意が必要です。
浄化槽が浮上している

大雨や地震で地盤がゆるむと、埋設された浄化槽が地中から浮き上がる「浮上」が発生します。周囲の土がめくれたり、マンホールが傾いたりするなど、外見にも明らかな変化が現れます。
浄化槽が浮上すると、接続されている配管が外れたり、内部装置が破損している可能性が高いです。配管が外れていない場合でも、内部の勾配が変わると汚水が逆流し、トイレや排水口からあふれるおそれがあります。
管理業者による点検が終わるまでは、浄化槽の使用を控えましょう。
浄化槽本体の漏水や配管が外れている
漏水とは浄化槽に亀裂や穴ができ、槽内の汚水が外部へ漏れる現象です。水位が低下すると、浄化槽は正常に機能しません。漏れた汚水は地中に染み込み、土壌や周辺環境を汚染します。
配管が外れると、槽内の汚水が地中に漏れるおそれがあります。外れた箇所から雨水や土砂が流入し、処理機能の低下につながります。
放流先に詰まりや異常が発生している
雨水や土砂が流れ込むと、浄化槽の処理水を排出する側溝や放流管が詰まります。
放流先がふさがれると処理水が流れず、槽内の水位が上昇します。結果、宅内の排水が滞り、水が逆流してトイレからあふれるおそれもあります。
災害時の浄化槽トラブル|実例から考える備え

災害時、浄化槽トラブルの実例から備えについて、以下の内容を解説します。
- 令和6年能登半島地震でのトイレ被害と浄化槽への影響
- 東日本大震災で多発した浄化槽の故障や配管の破損
- 避難所ではトイレ不足や衛生環境の悪化が深刻化
令和6年能登半島地震でのトイレ被害と浄化槽への影響
令和6年能登半島地震では、地盤の隆起により多くの浄化槽が被害を受けました。
地下に設置された浄化槽は、地盤のゆるみや雨水の影響で浮き上がることがあります。実際に、同地震では浄化槽が浮上した事例も確認されています。
屋外に設置されたブロワーが浸水や破損により停止したケースも発生しました。浄化槽は下水道のように長い宅外配管を必要としない構造のため、地震や水害に強いとされています。
能登半島地震のように想定を超える地盤変動が起きた場合には、被害を避けられないこともあります。「浄化槽は災害に強い」と過信せず、非常時に備えたトイレ対策をあらかじめ準備しておくことが大切です。
» 能登半島地震災害対応と避難所トイレシステム(外部サイト)
東日本大震災で多発した浄化槽の故障や配管の破損
2011年の東日本大震災では、太平洋沿岸を中心に津波による被害が発生しました。津波の影響を受けた地域では、多くの建物とともに浄化槽も流失や破損が確認されています。
環境省の報告によると、住宅地では浄化槽が道路に転がっていた事例も見られました。とはいえ、浄化槽本体の耐久性は高く、環境省などの調査でも裏付けられています。
被災地で不具合が確認された浄化槽を対象に調べた結果は以下のとおりです。
- 浄化槽本体の破損率は約3.8%
- 浄化槽の浮上発生率は地域差あるが約10%前後
配管の外れや勾配異常といったトラブルは多く発生しましたが、本体に限って見れば、非常に高い耐久性があるといえます。
避難所ではトイレ不足や衛生環境の悪化が深刻化

避難所ではトイレの衛生環境が悪化しやすく、感染症や健康被害のリスクが高まります。
災害時には、下水道の仮復旧までに平均30日かかるとされ、水洗トイレが使用できません。仮設トイレの設置には発災から約3日かかるといわれており、不衛生なトイレを使わざるを得ない状況が生じます。
仮設トイレが届かなかった避難所では、排泄物があふれたトイレが見られました。水分や食事を控える人が増え、脱水症状やエコノミー症候群になった事例もあります。
トイレ環境が整わなければ、命に関わる深刻な健康リスクを招きます。災害時に備え、トイレを含めた衛生対策の準備が欠かせません。
» 避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン(外部サイト)
» 避難所における トイレの確保・管理ガイドライン(外部サイト)
災害時に最低限備えたい衛生用品

災害時・停電時に最低限備えたい衛生用品について、以下の内容を解説します。
- 携帯トイレや組立式の簡易トイレ
- トイレットペーパーやティッシュペーパー
- ゴミ袋や排泄物用の凝固剤
- 手指消毒用アルコールや除菌スプレー
- 除菌ウェットティッシュやおしりふき
携帯トイレや組立式の簡易トイレ
災害時に水が使えない状況では、トイレの確保が大きな課題になります。そんなときに役立つのが「携帯トイレ」と「簡易トイレ」です。
携帯トイレは、袋と凝固剤がセットになった非常用トイレで、すぐに使用できます。個包装で清潔に保管できるため、緊急時でも安心して使えます。便座がなくても使えますが、便座にかぶせると通常のトイレに近い感覚で使用可能です。
簡易トイレは、便座付きの箱型タイプなどがあり、自宅や避難所での長期使用を想定しています。袋と凝固剤をセットして使い、使用感も一般的なトイレに近いのが特徴です。
どちらにするか迷った際は、ひとまず携帯トイレを備えておきましょう。コンパクトで保管しやすく、非常袋や引き出しにも収納できます。
在宅避難時も断水によってトイレが使えなくなることがあるため、携帯トイレが役立ちます。以下の備蓄量を目安にしてください。
- 1人1日あたりのトイレ回数は約5回と想定する
- 1人あたり7日分として約35回分を備蓄する
- 3人家族なら100回以上の使用量を想定する
- 乳幼児や高齢者がいる家庭は多めに準備する
トイレットペーパーやティッシュペーパー
過去の大規模災害では、トイレットペーパーの不足により、多くの人がトイレに関する不便を感じました。
多くの人が使用するため、排泄物を隠すために通常より多く使われる傾向があります。汚れの拭き取りや嘔吐物の処理にも使われるため、消費量が増加します。
経済産業省によると、1人が1週間に使うトイレットペーパーは約1ロールですが、災害時のことを考えて少し多めに備えるのが安心です。
1か月分の備蓄を想定すると、3人家族で24ロールが目安となります。12ロール入りのパックを2つ用意しておけば、1か月分の備えとして十分です。
備蓄方法は、ストックしていた1パックを使い始めたタイミングで新たに1パックを補充するのが理想的です。日常の買い物が災害への備えにつながります。
ティッシュペーパーは水に溶けないため、通常トイレに流せませんが、災害時には代用品として役立ちます。
ゴミ袋や排泄物用の凝固剤
災害時には自宅での在宅避難が可能なケースも多くあります。在宅避難ができる場合は、自宅の洋式トイレを簡易トイレとして活用できます。
便器に大きめのゴミ袋をかぶせ、用を足したあとに凝固剤を入れて処理する方法です。使用済みの袋は一時的に保管する必要があるため、におい対策として消臭袋も一緒に備えておくと安心です。
携帯トイレに比べて準備が手間に感じられることもありますが、慣れると難しくありません。費用を抑えて多めに備えられる点も大きなメリットです。家族の人数が多い家庭や、長期の備蓄を想定する場合におすすめの方法です。
手指消毒用アルコールや除菌スプレー
災害時には断水により、普段のように手を洗うことが難しくなります。手についた汚れや菌が原因で感染症や食中毒を引き起こすおそれがあります。
水が使えない状況に備えて、手指消毒用のアルコールや除菌スプレーを用意しておくと安心です。手軽に清潔を保てるため、非常時の衛生管理に欠かせないアイテムです。
除菌ウェットティッシュやおしりふき
水が使えない災害時には、大人にとってもおしりふきが心強いアイテムです。お尻を清潔に保つことは、感染症の予防だけでなく、精神的な安心にもつながります。
おしりふきは体を拭く用途にも使えるため、全身のケアにも役立ちます。赤ちゃん用のおしりふきは、肌にやさしい低刺激仕様なので、大人が使っても快適です。
防災グッズとしても人気があり、顔に使用したい場合は「顔にも使える」と記載されたノンアルコール・無香料タイプを選ぶと安心です。
家庭にあると安心な備品

家庭にあると安心な備品は以下のとおりです。
- 充電式ポータブル電源や小型発電機
- 飲料水とは別に備えておくトイレ用の生活用水
ポータブル電源or発電機
災害時は停電が長引き、夜間は照明が使えないことが多くあります。暗い中での生活は転倒などの事故や、衛生面でのトラブルにつながります。
夜間にトイレを使う際も、明かりがないと安全が確保できません。ポータブル電源や小型の発電機があれば、懐中電灯や簡易照明を使え、安全性が高まります。携帯トイレの確認や処理にも、最低限の明かりは欠かせません。
電源に余裕があれば、スマホの充電や小型冷蔵庫、電気ポットの使用も可能です。非常時に最低限の機能を保つためにも、電源の備えがあると安心です。
飲料水とは別に備えておくトイレ用の生活用水
災害時は飲料水の確保が最優先ですが、トイレや手洗いに使う生活用水も欠かせません。浄化槽や下水道が復旧しても、水がなければ水洗トイレは使えず、不衛生な状態になります。
ウェットティッシュがあっても、手をすすいだり汚れを洗い流したくなる場面は少なくありません。飲料水とは別に生活用水を備えておくと安心です。
生活用水の確保法には、以下の例があります。
- 入浴剤を使わず風呂の残り湯をためておく
- ポータブルタンクや雨水タンクに水を備蓄しておく
まとめ|「災害に強いトイレ環境」は準備が9割

家族全員で「災害時のトイレ対応ルール」を共有しておこう
災害が起きてからでは、トイレの準備や対応を冷静に考える余裕はありません。「どこで」「何を使って」「どう排泄するか」を、日頃から家族で話し合っておくことが重要です。
小さな子どもや高齢者、介助が必要な家族がいる場合は、状況に応じた備えが欠かせません。
たとえば、家具を手すり代わりに使えるように配置したり、ポータブルトイレを設置しやすい場所をあらかじめ決めておくことで、非常時にも落ち着いて対応できます。
衛生用品の備蓄がトイレの不安を軽減
災害時に電気や水道が止まっても、排泄は誰にとっても避けられません。トイレ環境が整っていないと、不衛生な状態が続き、排泄を我慢することで体調不良のリスクが高まります。
トイレが使いにくい、安心して使えないといった状況は大きなストレスとなり、心の余裕も奪われます。トイレ対策は快適さだけでなく、命と健康を守るための備えです。
トイレ対策は後回しにされがちですが、災害時には重要な生活インフラです。事前の備えは衛生環境を守るだけでなく、精神的な負担も軽減します。
トイレの備蓄は、自分と家族の命を守るための防災対策です。突然の非常時に備えて、今日から準備を始めましょう。