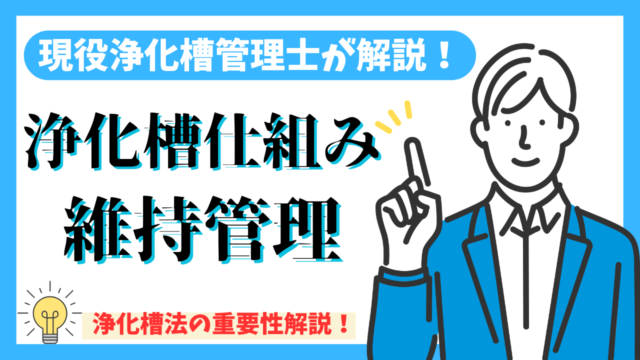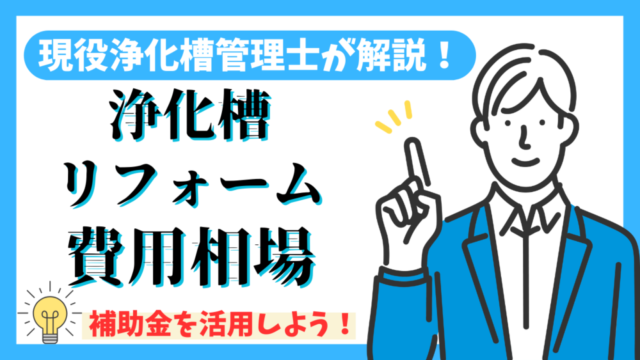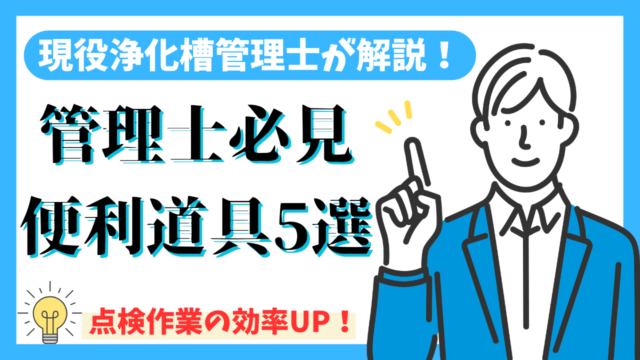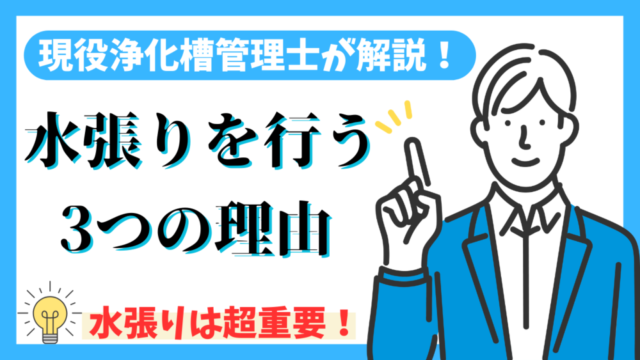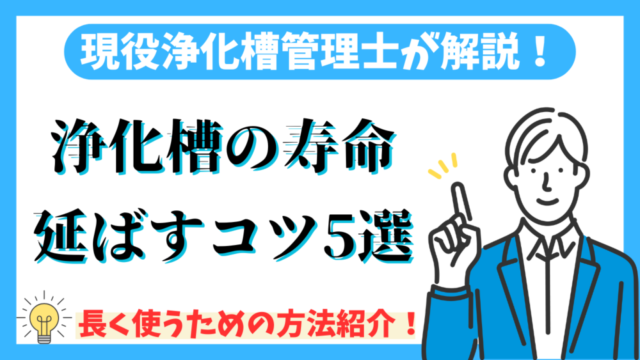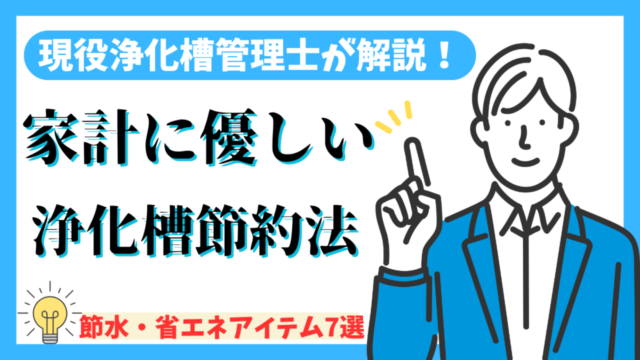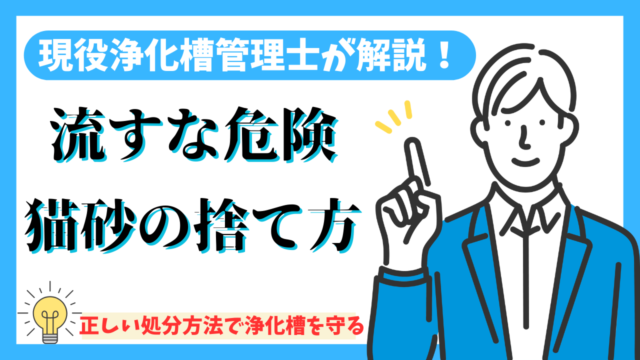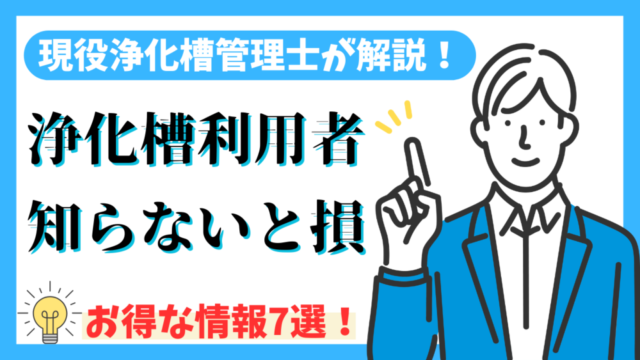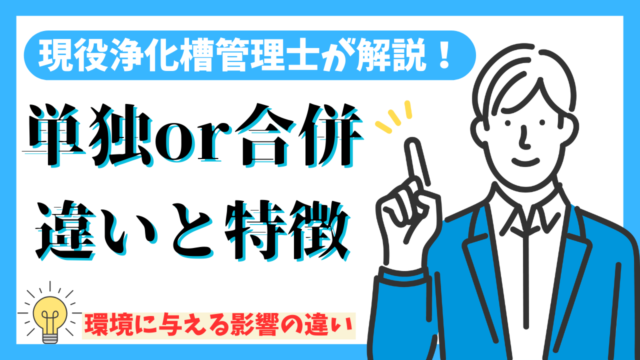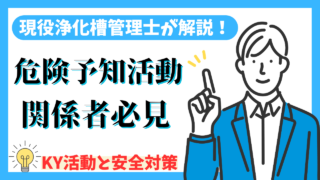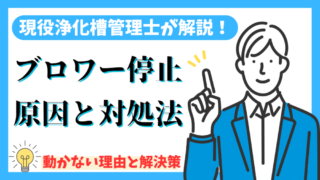【浄化槽が臭う原因】よくある5パターンと今すぐできる対処法!
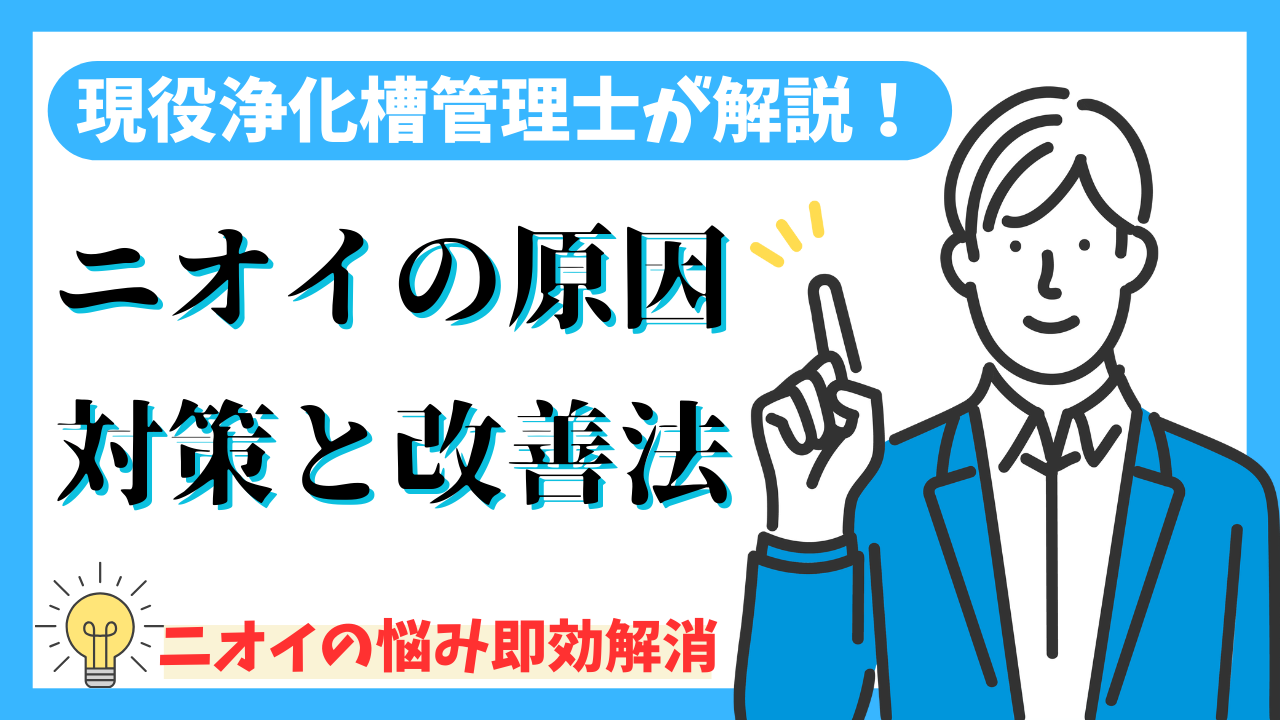
「浄化槽の臭いが気になる…」と悩む方は多くいます。臭気は生活の快適さを損なうだけでなく、近隣トラブルの原因にもなります。
臭気の原因は特定しづらく、対策を見つけるのが難しいです。この記事では臭いの原因5選と対処法を解説します。
記事を読めば臭いの原因を特定し、適切な対策ができます。臭いの問題を解消し、快適な生活環境を取り戻しましょう。
臭いの主な原因は以下の5つです。
- ブロワーの劣化や故障により臭気が発生する
- マンホールのヒビや隙間から臭気が漏れる
- 害虫の発生により臭気が生じる
- 維持管理が行われていないと臭気が発生する
- 水の過剰使用により処理容量を超えて臭気が発生する
以下の動画でも、浄化槽の臭いについてわかりやすく解説しています。
浄化槽の臭気はブロワーが原因|故障時の影響と対策

ブロワーは浄化槽の「心臓」といえる重要な装置です。槽内の微生物は酸素を必要とし、ブロワーがエアーを供給しています。
ブロワーが故障すると酸素の供給が不足し、好気性微生物が死滅します。浄化処理が停止し、臭気の発生につながります。
微生物不足が原因?シーディング剤で浄化槽の臭いを改善
新築やリフォーム後に新設した浄化槽では、微生物が十分に定着しておらず、臭気が発生しやすい状態です。
微生物のバランスが崩れると処理が不十分になり、臭気の原因になります。臭気が発生した場合は、シーディング剤の使用が効果的です。
シーディング剤は微生物の働きを活性化させ、脱臭効果をもたらします。使い方は簡単で、トイレにパックを流すだけで槽内の環境が整います。
マンホールの劣化に注意!ヒビや隙間から漏れる浄化槽の臭い

マンホールが劣化すると隙間から臭気が漏れ出します。臭気や煙は上昇するため、隙間から外部に拡散します。
経年劣化により耐久性が低下するため、定期的な点検が必要です。マンホールを交換すると、臭気問題を解消できます。
ヒビや欠けのあるマンホールは破損するリスクがあるため、早めに交換してください。
浄化槽内に潜む害虫の駆除方法と予防策

害虫によって臭いが発生する主な原因は、以下のとおりです。
- 幼虫が動き回りスカムが崩れる
- 幼虫がスカムを食べる
- 幼虫の排泄物が強い臭気を放つ
槽内は年間を通して暖かく、虫にとって好都合な環境です。スカムとは槽内に浮かぶ汚れやカスのことを指します。
スカムの様子は、以下の動画で確認できます。
マンホールの隙間やヒビから虫が侵入し、槽内で卵を産んで繁殖が進みます。
特にアメリカミズアブによる被害が多く報告されています。アメリカミズアブの幼虫は、強い臭気を放ち、見た目も不快です。
害虫対策としては、槽内に殺虫プレートを設置する方法や、粉末薬剤を散布する方法があります。浄化槽清掃して汚泥の引き抜きも効果的です。
対策により害虫の発生を抑え、1年を通じて快適な環境を保てます。
浄化槽の臭気と故障を防ぐ|日常点検と維持管理のポイント

浄化槽の維持管理については、以下で解説します。
- 浄化槽管理の基本|保守点検・清掃・法定検査の重要性
- 節水・省エネで浄化槽の負担を軽減|今日からできる習慣
浄化槽管理の基本|保守点検・清掃・法定検査の重要性
浄化槽を長期間維持するには「保守点検・清掃・法定検査」が重要です。維持管理を怠ると、以下の問題が発生します。
- 消毒剤が不足する
- 汚水が垂れ流しになる
- 環境に悪影響を与える
- 漏水や湧水のリスクが高まる
- 悪臭が発生する
- 浄化機能が低下する
- 浄化槽が破損する
- 近隣に迷惑がかかる
維持管理を怠ると悪臭が発生し、周囲に迷惑をかけるだけでなく、環境汚染の原因にもなります。
浄化槽所有者は、排水に対して責任を持ち、保守点検・清掃・法定検査を実施する義務があります。維持費や処理費がかかることを理解し、適切な管理を徹底しましょう。
過剰な水使用に注意|浄化槽への負担を減らす節水習慣
無駄な水の使用は浄化槽に負荷がかかり、槽内の滞留時間を短くします。汚水を処理するには、一定の時間が必要です。過剰に水を使用すると、処理容量を超えてしまいます。
無駄な水の使用は控えましょう。日々の習慣を見直すと水道代の節約に加え、電気やガス代の削減にもつながります。
まとめ

臭いの原因を解決する方法は以下のとおりです。
- ブロワーの稼働状況を確認する
- マンホールの状態を点検する
- 浄化槽周辺の虫の発生を確認する
- 維持管理の点検を受ける
- 浄化槽清掃を行い水の無駄遣いを防ぐ
嗅覚には個人差があるため、現場で確認しなければ臭気の原因を特定できない場合があります。状況に応じた対応が求められるため、管理会社へ相談するのが確実です。
臭気対策としては、ブロワーやマンホールの点検、害虫の防除、定期的な維持管理が重要です。